これからのパブリックのトイレを考える
公共空間における個人の自由を求めて
鈴木謙介(社会学者)| 永山祐子×萬代基介×羽鳥達也(建築家)× 門脇耕三(建築学者、監修)
『新建築』2017年5月号 掲載
これまでLIXILと新建築社では、姉妹誌『新建築住宅特集』にて玄関、間仕切り、水回り、窓について企画を立て考察してきました。今回は明治大学専任講師の門脇耕三氏を監修者として迎え、永山祐子氏、萬代基介氏、羽鳥達也氏、の3名の建築家にテナントオフィスビルのこれからのトイレを提案してもらいました。また、社会学者の鈴木謙介氏にパブリックトイレの現状や課題などについて論文を執筆いただき、それらを元に座談会を行い、パブリックトイレのあり方について考えました。(編)
パブリックトイレの現状と課題
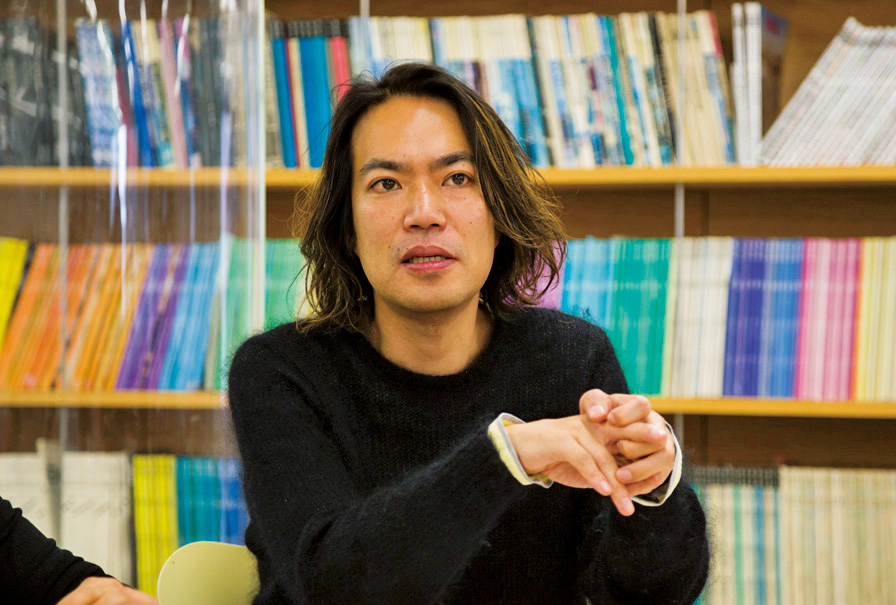 門脇耕三(かどわき・こうぞう)
門脇耕三(かどわき・こうぞう)1977年神奈川県生まれ/ 2000年東京都立大学卒業/2001年同大学大学院修士課程修了/ 2001?05年同大学助手/ 2005?07年首都大学東京助手/ 2007?12年首都大学東京助教/ 2012年?明治大学専任講師/ 2012年?アソシエイツ設立・パートナー
ニューヨーク市では2017年から、共有スペースのない公共のトイレはすべてジェンダーニュートラル(性別不問)にすることが法律で義務付けられました。
それを建築家の浅子佳英さんに教えてもらい、いろいろと考えてみたのですが、選択の余地のない狭義の生物学的な性別にしたがって特権的に入れる空間や、入れない空間が公共の場に存在するということは、見方を変えれば野蛮なことではないかと思いました。私たちは、男女で分けられたトイレをごく当たり前に受け入れていますが、数十年後にはそのように性別で空間を分けることは文化的に成熟していない古い考え方だと未来の人たちに揶揄されているのかもしれません。これについてアメリカ国内でも議論になっているようで、保守色の強いノースカロライナ州では、出生証明書に記載された性別に合わせたトイレ使用を義務付ける州法が可決されたのですが、つい最近撤回されました。そこでLIXILの方にもこの問題について聞いてみたところ、衛生機器業界では既に対応に追われているそうです。2020年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されますから、国際化対応のひとつとして、ジェンダーニュートラルなトイレを考える必要があるということでした。
しかし、誰も気付かないうちにトイレが変わっていたとなると気持ちが悪いと思い、トイレがまさにこれから変わっていくであろう今、少なくとも建築界では、さまざまなトライアルに基づいた議論があるべきだと思います。その考えにご賛同いただき、今回の企画が立ち上がりました。まずは議論の前提として社会学者の鈴木謙介さんにパブリックトイレについての論文をご執筆いただき、現状や課題などを共有した上で、3名の建築家にこれからのパブリックトイレを提案いただきました。今回はトイレの問題を通じて、社会参画しやすい公共空間のあり方を考えたいと思っていますが、空間は時に社会のあり方を規定してしまいます。例えば鈴木さんの論文によると、男女で分けられた空間は、人間が男と女のふたつに分けられるという社会的メッセージを発するというように、トイレのあり方は、人びとの倫理観や人間観にも影響を及ぼしているというわけです。また、今回の問題は建築計画学的にも興味深く、トイレの配列などの常識が変わるとしたら、われわれが見知ったビルディングタイプそのものが組み立て直される可能性があります。つまり今回の問題は、「たかだかトイレ」の話題ではなく、広範な議論を必要とする刺激的なトピックだということです。この企画がぜひ建築界での議論の端緒になればと思います。
(門脇耕三)
「人に合わせる」公共空間の設計――管理から自由へ
鈴木謙介(社会学者)
公共空間における多様性への配慮
提供:鈴木謙介
 鈴木謙介(すずき・けんすけ)
鈴木謙介(すずき・けんすけ)1976年福岡県生まれ/ 1999年國學院大学卒業/ 2001年法政大学大学院修士課程修了/ 2003年東京都立大学(現、首都大学東京)大学院博士課程単位取得退学/ 2008年関西学院大学社会学部助教/ 2009年?関西学院大学准教授
公共空間のあり方が、さまざまなかたちで問われるようになっている。グローバルな人の流れの増大により、公共空間を共にする人びとの多様性が増し、またそうしたさまざまな人びとがそれぞれ不快な思いをすることのないように配慮することが求められるようになっている。もちろん日本国内においてこれまでもさまざまな人びとが公共空間にいたのだが、グローバル化した世界では、「海外ではこのような配慮がある」といった情報も世界的に共有されるために、これまで以上の取り組みが必要になっているのだ。ここではその例として「パブリックトイレ」について考えてみたい。他の国と比べても、誰もが無料で自由に利用できるトイレが多いのが日本の特徴だが、それだけに「トイレの公共利用」についての課題も多い。例えば、利用シーンの多様化。近年、花火大会や野外音楽フェスなどのイベント開催時に、仮設トイレの不足が利用者の大きな不満になったり、コンビニなど近隣施設への迷惑に繋がったりする場面が目立っている。また都市部でのハロウィンに見られるように、イベント時にはトイレがコスプレ衣装に着替えるための場所になることもある。商業施設においては、特に女性用トイレのパウダールームを豪華にすることが集客のウリになっているし、男性の場合も個室でスマホを利用するといった例が増えているという。あるいは、利用者の多様化、高齢化が進むことで和式では用を足せない高齢者が増加しているが、そうした人びとがよく利用する施設の中でも、野外の公衆トイレしか用意されていない寺社仏閣などで、トイレの改修が進んでいないケースが見られる。また洗浄機能などの付いた多機能型トイレの普及も進んでいるが,その高齢者だけでなく外国人の利用者も含め、誰もが見ただけで操作方法を理解できるものになっているとは言いがたい。
こうした変化を,ひとまず「利用者および利用ニーズの多様化」としておこう。利用のあり方が多様化すれば、当然パブリックトイレのあり方も変化を迫られることになる。それにもかかわらず、パブリックトイレのあり方を巡る社会的な議論は盛んではなく、あくまで「個人的な不満」としてネット上で見かける程度である。これでは新しいトイレを提案するにも手がかりが少なすぎる。そこでこの論文では、パブリックトイレを考える上で材料となる視点を、社会学の立場から紹介し、またなぜパブリックトイレをめぐる議論が盛り上がらないのか、どのような観点から公共空間について考えるべきなのかといった点についても論じることにしたい。
マイノリティにとってのトイレ
パブリックトイレを巡る議論の中でもよく持ち上がるのが、セクシャル・マイノリティとの関係だろう。いわゆる「男子用」「女子用」と区分されたパブリックトイレは、体の性と心の性の不一致を抱える人びとや、身体的な性と見た目の性が異なる人びとなど、性の多様なあり方に対応できないだけでなく、そうした人びとがトイレを利用するたびに、自分には社会的な居場所が用意されていないのだという感覚を抱かせるという問題がある。では、なぜそのような感覚を与えるのか。「男性用」「女性用」(あるいは「青」「赤」といった記号)で示されるトイレの区分が、「この世界の人間はすべて男か女に分けられる」というメッセージを発するからだ。心の性、ないし体の性に合わせて利用すればよいのかといえば、そうではない。「トランスジェンダー」という言葉が示すとおり、セクシャル・マイノリティにとっての性のあり方とは越境的なものである場合が多く、本人ですら「自分はどちらのトイレに入ればいいのだろう?」と立ち往生してしまうケースも見られるのだ。すなわち「この世には男と女しかいない」というメッセージが公共空間に体現されていることで、その「どちら」とも言い切れない人びとは、パブリックトイレを利用することに戸惑いを覚えるだけでなく、「自分の性をはっきりと示せない人は、不完全な人間である」という社会からのメッセージを受け取ることになり、それゆえ社会的な居場所のなさを痛感することになるのである。話を広げるなら、さまざまな利用者や利用ニーズの拡大は、これまで以上に「公共空間を利用する際の不全感」を利用者に与えることに繋がっているとも言えるだろう。
では、用のあり方の多様化に、社会は、あるいはより具体的に設計者はどのように対応すべきだろうか。ひとつの考え方は、「利用の多さ」で割り切るという合理的、功利主義的な考え方だろう。ありとあらゆるニーズに対応できる設備を、あらゆる人に向けて用意するのは物理的に困難である。それゆえ、例えば高齢者の利用が多ければ高齢者向けに特化したトイレを設置するといった方針が、まずは考えられる。しかしながらこの考え方には、非常に大きな問題がある。功利主義的な発想はすぐに「マイノリティに配慮した設備は、マジョリティの余裕がある場合に善意で用意してあげるものだ」という理念に基づく設計へと繋がるからだ。東日本大震災の折、避難所生活を送るマイノリティにとってもっとも苦しかったことのひとつが、トイレの問題であったという。性同一性障害を抱える人が利用するトイレを用意したいと申し出ても、誰も彼もが被災者の中、「そんな余裕はない」と断られたというケースがあった。あるいは視覚障害者が、近くの人に毎回トイレへと案内してもらうことを申し訳なく思い、水を飲むことすら控えていたというケースも耳にした。利用者の多さを根拠にした「多様性への配慮」は、マイノリティであることはマジョリティにとっての負担であり、マイノリティは社会のお荷物だというメッセージを発することに他ならないのである。
柔軟な利用に対応する
物理的な資源の限界を抱えながら、多様な利用者が不快な思いをしないような設計を行うのは、どのような場合においても厄介な問題だ。特にマイノリティを巡る問題では、利用のあり方だけでなく、そのあり方に対応するアイデンティティに関する課題も考慮しなければならない。というのも、性同一性障害の人が利用しやすいトイレを設計することと、相手に「性同一性障害の人」というレッテルを貼って特別扱いすることは別のものだからだ。足が弱いから電車で座りたいというニーズを持つ人が、他方で「高齢者扱いは嫌だ」というのと同じで、「マイノリティ向けの配慮」をマジョリティとは別に用意することが正解とは限らない。
このような多様性とアイデンティティの問題は、社会学が扱う課題の中でも最も難しいもののひとつであり、それゆえにひとつの正解を導くことができないものでもある。私自身、社会学者としてこの問題に答えることはできない。だが、パブリックトイレの利用に際して不快な思いをする人を減らすという点では、いくつか考えられることがありそうだ。前提として、トイレを利用する目的の大部分は個人的なものであるということがある。用を足す以外にも、スマホを用する、メイクを直す、あるいは単に休憩するとか、ひとりになるといったことまで広げても、多くは個人で、自分の目的のために利用する。例外は「友だちと秘密の話をする」といったケースだろうが、これも「他から切り離された場所」としてトイレを利用するという点では「ひとりで利用する」目的と共通するところがあるだろう。そうすると重要になるのは、その目的がどのようなものであるか、トイレがその目的を果たすのに最適な場所になっているかどうかということではない。「他の場所から切り離された状態で自分の用事を済ませる」のに使えるのであれば、多少不便であろうとトイレが選ばれるのである。だとすれば対応すべきは「ひとりの場所」の設計ではない。むしろ「ひとりの場所」を利用しやすくするためのプロセスの設計、つまりトイレへのエントランスや動線こそが、「多様な人が、多様な目的でトイレを利用する」ことの快適性を高めるのではないだろうか。具体的な設計を提案するのは私の役割ではないが、例えば、トイレへの動線を長い廊下にして、その途中にパウダールームや個室への入口を用意し、最奥部に男子用小便器を設置するといったデザインはどうだろうか。これがすべての問題を解決するわけではないが、利用者がそれぞれの事情で「他から切り離された場所」に移行するプロセスを、ある程度の多様性をもって用意できるのではないかと思う。
こうした案をここで提案したのは,多様な利用のあり方に対応するデザインが、文字通りの「多様なデザイン」を意味するわけではないことを示したかったからだ。どちらかと言えば多様性に対応するのは、その多様さにこたえる「柔軟さ」を有したデザインであろう。その柔軟さをどのように利用するかは、まずもって利用者、そして、利用者の集団を包含する社会が、利用の中で生み出していくものなのである。
管理から自由へ
ここで問題の中心は,ふたたび社会の方へと移る。つまり、利用者が多様な利用のあり方を生み出していくのだとすれば、設計やデザインに限界があるとしても、ある程度は運用によってカバーできる。では、パブリックトイレを含む公共空間で、そうした多様な利用の提案が進まないのはなぜだろうか。その背景には、「公共空間」を巡る日本ならではの事情がある。
欧米で「パブリックスペース」といえば、基本的には各人がどのように利用しても構わない場所のことを指す。公園であれ広場であれ、そこで日光浴だろうがヨガだろうが政治集会だろうが、誰かの自由を侵害しない限りどのような利用でも許容される。これは「公共圏」というものが権力に対して物申す市民の自由な領域として立ち上がってきた歴史的な経緯と、実際に公共空間がそのように利用されてきたという事実によって支えられる理念であると言えよう。
一方で世界の中でも特に日本は、こうした「自由に利用できる公共空間」という発想が乏しい。むしろ「公共」という言葉が示すのは、各人が自分のエゴを抑制し、集団のため、全体のためになることを進んで行うという意味だ。こうした発想が公共施設に適用されれば、どのような場所であっても「みんなが使う場所なので、お互いのために身勝手な利用はやめましょう」ということになる。それが行き着くところは、「不快になる人がいるので、公共の場所では定められた利用以外は禁止します」という考え方である。もちろんこの場合の「不快」とは、社会のマジョリティが感じるとされている価値観にもとづくものであり、個々の利用者のものではない。
しかしながらこうした発想で「公共」を語っていても、この記事で述べてきたような多様な利用のあり方に開かれた施設をデザインすることができないのは明らかだ。「みんな」という名の公共的マジョリティに適合的な施設を設計し、それ以外の人を合わせるのではなく、多様な人と利用に合わせて公共空間を設計するという逆向きの発想が求められているのである。
このコラムの関連キーワード
公開日:2017年12月25日

