インタビュー 1
これからの都市と住まいを考える──ショッピングモール、公園2.0、フードトラックから
速水健朗(ライター、編集者)+浅子佳英(建築家、プリントアンドビルド)

浅子佳英氏(左)、速水健朗氏
アルビン・トフラーの未来予測
浅子
速水さんは『東京どこに住む?』のなかで、アメリカの評論家、アルビン・トフラーの未来予測を取り上げています。未来予測というのはおおよそ当たらないものだけれど、彼の場合はことごとく当たっていて、ただ、唯一当たらなかったのが「都市がなくなる」という予測だと書かれていますね。
速水
トフラーが『第三の波』(鈴木健次+桜井元雄訳、徳山二郎監修、日本放送出版協会、1980/原著=1980)は世界的なベストセラーなんですが、今読むとおもしろいんです。トフラーは、コンピューターが普及したらどうなるかを予測しています。『第三の波』が書かれた1970年代の都市は、騒音や大気汚染などの公害や道路の渋滞や電車の混雑が酷くて、非人間的な生活環境だと思われていました。それがネット通販やリモートワークが普及すれば、人はそこから脱出できるとトフラーは予言した。コンピュータの普及で可能になることはすべて予測したトフラーが、都市の消滅だけ外しているのがとても興味深い。
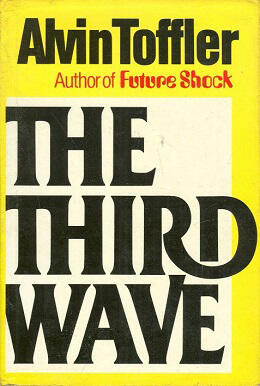
アルビン・トフラー『第三の波』
浅子
マット・リドレーは、最近日本語訳が出た『人類とイノベーション──世界は「自由」と「失敗」で進化する』(大田直子訳、NewsPicksパブリッシング、 2021)のなかで、都市の重要性について指摘いました。多くのイノベーションは、ひとりの天才ではなく、すでにあるアイデアを展開したり、β版をつくる人がいることで生まれている。だとするなら、多様なバックグラウンドをもった人々が集まる場所が必要で、そうなると都市は解消されるどころか、今日ではますます重要なものになる。
速水
トフラーの予言が外れた理由に、リドレーが答えを出しています。でもほんとコロナ禍の何が苦しいかって、バーでたまたま隣りに座った知らない人の話を聞くといった機会が失われたことですよ。ライターとかジャーナリストって、そういうものの積み重ねみたいなところがあるので。僕にとっての都市は「飲み屋で隣になった人がすごい人だったということが当たり前に転がっている場所」です。たまたま会ったフィンランド人からの留学生が、ネット経由で僕のラジオのリスナー聞いたことがあった。それだけでもびっくりですけど、彼の担当教授は僕が書いた『ラーメンと愛国』(講談社現代新書、2011)のイギリス版みたいな本を書いてたんです。コロナ渦直前の時期の思い出ですね。
浅子
いまの話を聞いて、東浩紀さんが『弱いつながり──検索ワードを探す旅』(幻冬舎、2014)のなかで紹介していた、アメリカの社会学者、マーク・グラノヴェターの「弱い絆(Weak Ties)」という考え方を思い出しました。新しい職場を探すときに、知人や職場の仲間といった「強い絆」に頼ったほうが自分の能力や資質をわかってくれているのでうまくいくと思われがちだけれど、実際にはまったく逆で、たまたま飲み屋で知り合った人のほうがうまくいくケースが多い。なぜなら、「強い絆」は自分の知り合いの知り合いなので、予測可能な範囲の転職先しか紹介してくれない。一方、たまたま知り合った人は、自分のことを知らないので適当な職場を紹介するのだけれど、そのことで未知の領域に踏み出すチャンスを与えてくれるというわけです。そう考えると、至るところで「弱い絆」が生まれる機会に恵まれているのが都市の最大の魅力なのかもしれませんね。
速水
ソーシャル・ディスタンス以前って、僕は距離の近さが大事ってずっと主張してたんです。僕がしていた取材のテーマは、例えばIT系企業のエンジニアがなぜ会社の近くに住むのかだったりしました。エンジニアたちって仲が良くて、休みの日も一緒にゲームしてたりするんですよ。みんな近くに住んでいて、仕事も遊びも区切りがなくなる。いいアイデアはえてしてオフのふとした瞬間に生まれたりする。
浅子
以前、この企画でもコクヨでワークスタイルの研究をされている山下正太郎さんに話を伺ったことがあるのですが(「ポスト・コロナの住まいとワークスタイル」)、やはり同じようなことをおっしゃっていました。アメリカのIT系企業の場合、アメリカ人は日本人のような会社人間は少ないので、日本の企業以上に社員をオフィスにつなぎ止めておくことが難しい。だからこそFacebookなどの企業では、オフィスをアミューズメント施設のような空間にしたり、立派なレストランやジムを併設して、その場所にいたいと思わせる工夫をしている。しかし考えてみれば、そのような手厚い福利厚生は、ある意味では日本の企業が伝統的に得意としていたことでもあります。昔ながらの日本の企業では、社員旅行や社内イベントがたくさんあって、社員は家族ぐるみの付き合いをしていました。その代わり、労働と余暇の区分が限りなく薄まっていき、社員はつねに仕事のことを考える環境に置かれる。それが一時期の日本企業の強みにもなっていたと言える。ただ、そうした強みが、近年では仕事とプライベートをきっちりと切り分ける欧米型の働き方が導入されることで失われていき、日本企業の競争力が弱まっていった一因になっているのではないか。サイバーエージェントはそのことに気がついているからこそ、社員をオフィスにつなぎ止めておく工夫をしているのかなと、いまの話を聞いていて思いました。
速水
まさに。そう考えるとリモートワークは、近接性の真逆なんですよね。僕はそんなのうまくいかないってずっと言い続けてたら、世間もいまそんな空気になってますね。
小さなものを見直すこと
浅子
実際、事務所を運営していても思いますね。結局大きくなるとひとりではすべてを見れないですから。家族の単位にしても、時代によって構成人数が変わってきました。日本の住宅は長年「ウサギ小屋」などと揶揄されてきましたが、それは4人の核家族を基準にしているからであって、少子化で家族の構成人数が減少している社会では、小さい家のほうがいい面もあるかもしれないと思うのですが。
速水
『今求められるミニマリズム』(2021)という映画のなかに、アメリカの建築家がアメリカの住宅は大きすぎるのではないかと考えて、必要最低限のサイズを追求するという話が出てくるのですが、僕はそれを見て「なんだ、日本の住宅じゃないか」と思いました(笑)。一方、日本の住宅はやや大きくなっています。昔の住宅はサイズが本当に小さくて、僕は1970年代の住宅に住んでいるのですが、いまどきの洗濯機はサイズ的にどれも置けないんです。すべての家具のサイズが大きくなっていると思いますよ。
浅子
ワンルームマンションがこれだけ供給されている都市というのは世界的に珍しいですよね。
速水
バブル期に投機目的でつくったワンルームマンションが多いんですけど、それが結果的に功を奏した気がします。東京都の1世帯当たりの人員は2.02人。4人に1人はひとり暮らしなのに、東京都は長らく単身者向けマンションの建築に規制をかけてます。大きい部屋に住めるのはいいって思うかもしれないですけど、単に狭いほうがいいことも多いですよ。メリットも多い。1人あたりの居住面積が狭いことのメリットは、まずは自然環境を破壊してないこと。持続可能性を考えるなら、自然環境を壊して人の住む領域を拡大していくのが一番悪い。
浅子
本当にそう思います。その一方で、日本の社会ではいまだに核家族信仰のようなものも根強くありますね。
速水
1人用、1.5人用、2人用、2.5人用くらいの細かさで住宅をつくるのがいいと思います。ひとり暮らしの若者が住みやすい大都市ランキングがあれば、東京は間違いなく1位だと思いますし。ちなみにトフラーの『第三の波』では、核家族はもはや維持できない、ただ守旧勢力がそれを維持しようとダメな政治を行うだろうということまで予測しているんですね。トフラー慧眼すぎる。
浅子
マジっすか……。トフラー、すごいですね。現状を的確に言い当てている。ともあれ、ワンルームマンションがたくさん供給されている点などは東京の強みでもあるので、小さなものを見直すことには可能性を感じます。
速水
最近興味があることに、“適正なサイズ”があるんです。いわゆる中流以上の人が自分のクラスに合わせた車を買おうとすると、なぜか海外のSUV(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)やミニバンなどの大きな高級車を買い求めてしまう。海外のSUVなどは、日本の道路や駐車場のサイズからすると大きすぎるのに。実際、車を買ったらガレージに入らなかった、なんてことも起こる。そこまでいかなくても、サイズに余裕がないと車庫入れのたびに神経をすり減らす。そこまで大きくない自動車を買ったほうが絶対に運転は楽しいはずです。でもなぜそうなってしまうのかというと、同じ値段で大きなものと小さなものがあると選択肢を与えられたときに、多くの人は前者を選んだほうが得だと考えてしまうからだと思うんですね。昔話の「舌切り雀」とか読んでもらわなかったのかな(笑)。
浅子
「トランスフォーマー」の敵役みたいな怖い顔をした大きな車に1人で乗っているドライバーを見かけますが、寂しくないのかなと思ってしまいます(笑)。
速水
だいたい家族用に大きい車が必要ってなるんですけど、実際に使われるのは1人のシーンで家族用の車が一番ムダが多い。都心部や新築マンションに機械式駐車場ができるじゃないですか。それをつくるときに、いまは1,900mmくらいを想定してつくる。20年前だったら1,800mmでよかった。都市のあらゆるインフラを大きいサイズ用に作り直すって、コストを考えると馬鹿馬鹿しい。エゴを抑えて小さい車に乗ればいいだけ。家もそうです。
浅子
先日、テスラのCEOで世界的な大富豪であるイーロン・マスクがコンテナハウスに住んでいるというニュースが報じられました。コンテナハウスの広さは三十数平米ほどで折りたたみ式らしいのですが、今後、ミニマルな可動式の住居がもっと供給されていく可能性もあるのでしょうか。
速水
1960年代のメタボリズム運動のときに、モジュール型の住居がコンセプトとしては出てきました。いいアイデアなんですけど、結局、定着しなかった。消費者がそれを選ばなかったんでしょうね。ただ早すぎた可能性はありますよね。
メタボリズムとフードトラック
浅子
リモートワークに関しては完全にリモート化されることはなさそうですが、とはいえコロナ禍が落ち着いても一部には残ると思うんですね。だとすると、住まいのなかに仕事場が入ってくることは避けられないので、住まいの未来を考えるためには、リモートワークとサイズの話を同時に提案していくことが必要だと思います。
サイズに関して言うと、僕はどの業界であれ、多様性やイノベーションを促すためにも新規参入をいかにしやすくするかということが重要だと考えているのですが、ショッピングモールに店を出すことは大きな投資でハードルが高い。その点、コスト的にも場所的にも小回りが効くのはフードトラックです。フードトラックであればどんな場所にも出店できますし、売り上げが芳しくなければ簡単に移動もできますし、初期投資が比較的安く済むので新規参入もしやすい。そういう意味では、今後注目すべきモデルになるのではないでしょうか。

フードトラック
ASIA CULTURECENTER(Unsplash)
速水
南池袋公園や渋谷の北谷公園など新しい公園は、フードトラックを入れることを前提につくられてます。今のフードトラックの流れってリーマンショック以後に生まれているんですよね。そして世界的に普及した。コロナ渦では店舗を維持できなくなった飲食店を大手が支援したりするような新しいシステムも生まれていたり、個人が立ち上げたものと大企業がうまく結びついている分野な気がします。
浅子
メタボリズムのときには建築として、いわばハードとして解こうとしたものを、コンテナハウスにせよフードトラックにせよ、現在は本当に動くもの、いわばソフトウェアとして解こうとしているんじゃないでしょうか。コロナが収まったらぜひ、フードトラックに研究を兼ねて飲みに行きましょう。本日はありがとうございました。
[2021年7月9日、プリントアンドビルドにて]
速水健朗(はやみず・けんろう)
1973年生まれ。ライター、編集者。メディア論、都市論など。主な著書=『ラーメンと愛国』(講談社現代新書、2011)、『1995年』(ちくま新書、2013)、『フード左翼とフード右翼──食で分断される日本人』(朝日新書、2013)、『東京β──更新され続ける都市の物語』(筑摩書房、2016)『東京どこに住む?──住所格差と人生格差』(朝日新書、2016)ほか。
浅子佳英(あさこ・よしひで)
1972年生まれ。建築家、ライター。2010年東浩紀とともにコンテクスチュアズ設立、2012年退社。2021年出版社機能を持った設計事務所PRINT&BUILD設立。作品=《gray》(2015)、《八戸市美術館》(2021)(共同設計=西澤徹夫)ほか。共著=『TOKYOインテリアツアー』(LIXIL出版、2016)。
このコラムの関連キーワード
公開日:2021年08月25日

