パブリック・スペースを創造する 4
ポストコロナの社会で未来像はいかに描けるか
山崎亮(コミュニティデザイナー) 聞き手:浅子佳英(建築家、タカバンスタジオ)

sturio-Lの主催で行われた「これからの介護・福祉の仕事を考えるデザインスクール」の様子(2018-19)
介護・福祉関係者を中心に全国各地から500人が参加した
提供=studio-L
ワークとしてのコミュニティデザイン
浅子佳英
今日はインタビューをお引き受けくださり、ありがとうございます。山崎さんと私は初対面ということもあり、ぜひ直接お会いしたかったのですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、やむをえずリモートで行うことになりました。山崎さんはコミュニティデザインという新しい領域を開拓し、これまで地域の課題を解決する活動をなさってきました。今回はCOVID-19以後、地域のあり方や人のつながりにも変化がおよぶと言われるなかで、山崎さんが今どのようなことを考えているか、ぜひこのタイミングでお話を伺いたいと思ったのです。
山崎亮
僕も楽しみにしていました。今日はよろしくお願いします。

浅子佳英氏
浅子
山崎さんの仕事で僕がとくに印象に残っているのは、2007年の泉佐野丘陵緑地のプロジェクトです。『コミュニティデザイン』(学芸出版社、2011)でもくわしく書かれていますが、公園の整備費用10憶円の一部を地域の人たちが運営管理するための育成プログラムに振り分け、継続的なマネジメントの基盤をつくるというもので、目から鱗が落ちる思いで読んだのをおぼえています。
コミュニティデザイナーとして注目を集めるようになったきっかけは東日本大震災後でしょうか。この震災で人と人とのつながりといったものが重視され、山崎さんもテレビなどを通じて積極的に発言されていました。また、震災以降、東北芸術工科大学にコミュニティデザイン学科を立ち上げたほか、現在では医療・福祉の分野でも活躍しています。ひとりのデザイナーがランドスケープからまちづくり、医療・福祉を横断する例はあまり聞いたことがありません。今日は多岐にわたる山崎さんの活動の変遷を少しでも紐解くことができればと思います。まずはコミュニティデザイナーとしてのこれまでの活動を振り返っていただけますか。
山崎
震災をきっかけとするなら、ひとつ前の阪神淡路大震災(1995)が大きいと思います。当時は神戸の近くに住んでいたこともあり、たいへんショッキングな出来事でした。このとき僕はランドスケープデザインを学ぶ大学3年生で、都市計画に近い緑地計画を扱う研究室に在籍していました。震災直後には研究室総動員で被災地の状況も調査しました。しかし、僕は壊滅的な都市を目の当たりにしてどうすればいいのかわからなくなってしまった。デザイナーを志すなら設計の道に進み、壊れないものをつくる仕事に就くべきなのですが、復旧の現場では全国から訪れたボランティアの人たちの市民活動の熱気も感じていました。壊れた都市と市民活動、このふたつを同時に見たことが僕の原点と言えます。ただ、このときの僕はデザインをやりたかったので、市民活動への興味にはふたをしていました。その後もオーストラリアに留学したり、大学院に進んだりしながらしばらくもやもやした時間を過ごします。結局、修士課程修了後はランドスケープデザインと建築設計を両方手がける事務所に就職し、そこで6年ほど設計の仕事を経験しました。
浅子
その時点では結局、市民活動のほうにはいかず、設計者の道に進んだのですね。
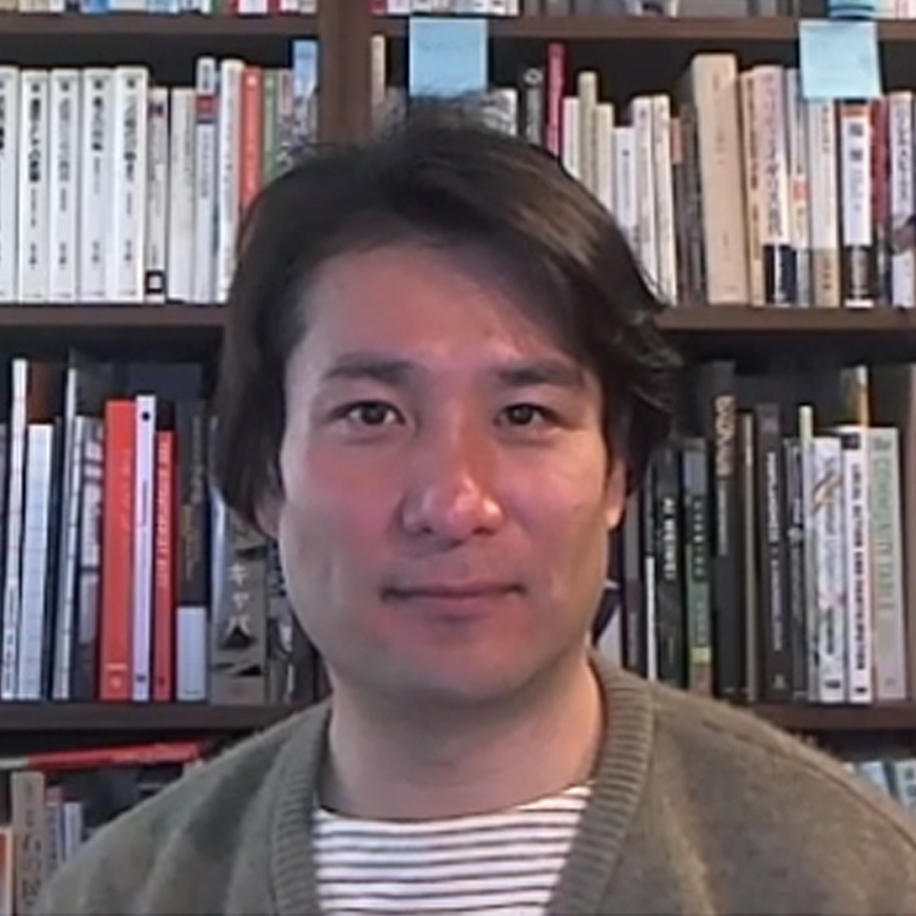
山崎亮氏
山崎
ところが、その就職先で決定的な出会いが待っていました。入社後しばらくは、ハーバード大学出身の社長の下でディテールを描いたり、数量計算したりしていたのですが、その方の奥さんが完全にワークショップ志向の人でした。大学で経済学を専攻していた彼女は、ワークショップはマーケティングであり、マーケティングしないのは考えられないと言って、自分が聞いてきた意見を旦那さんのプランにねじ込んでいくんです。僕はあっけにとられて見ていたのですが、あるときから彼女のお手伝いをすることになりました。最初は抵抗もありつつ、次第に奥さんの言うことは正しいかもなと思いはじめ、気づくとワークショップ側の人間になっていました。震災直後に見たボランティアの人たちの姿と建築設計の仕事が結びついたのはこのころだと思います。2005年に退所するときにはもうワークショップと設計の両輪でやっていこうと決めていました。
浅子
奥さんの影響が山崎さんの進む道を決めたのですね。独立したてのころはまだワークショップ一辺倒ではなく、設計の仕事もしていましたよね?
山崎
はい、設計からワークショップへと完全に重心を移すのはもう少し後のことです。独立後、しばらくはモノをつくりたいといううぶな葛藤があったのですね。2005年にstudio-Lを設立した直後は、図書館や公園をつくる前段階でワークショップをファシリテーションしてほしいといった依頼が大半でした。ちょうど市民参加を重要視する機運が高まっていた時期でもあります。ところが、しばらくこうした仕事を引き受けつつ、そちらに力を入れると設計にまで手が回らなくなることもわかってきた。地域の人たちの意見をまとめながら、大量の図面を描き、数量計算をこなすのはたいへんなことでした。そういう時期が2、3年続き、僕がこのまま設計にこだわり続けると事務所が立ち行かなくなってしまうと悟ります。そこで僕たちは、設計のための条件をつくる側に回る決断をしました。クライアントに掛け合って、デザインの部分は信頼できる設計者に分担してもらうようにしたのです。それがその後のstudio-Lの型をつくるのですが、形をつくる魅力に惹かれてデザインを勉強したわけですから未練もありました。その一方で、まだあまり知られていないワークショップの領域にも魅力を感じはじめていたのです。
ワークショップをとりまとめ、設計者が具現化するためのフレームワークづくりに注力しようと決めたとき、信頼できる設計者にきっちり引き継ぎ、かならず実現してもらうことをポリシーにしました。それからしばらくは試行錯誤です。どの程度条件を整理すれば、設計者に適切に引き渡せるか。基本設計まで僕たちが描いてしまうと相手はやりづらいだろうとか、それならダイアグラムをつくってゾーニングの手前まで与件を整理しょうとか、設計者に応じてスタディを繰り返していました。
浅子
たしかにその人や事務所によっても設計の進め方は違いますし、さじ加減が難しいですね。現在ではある程度最適解が見つかったのでしょうか?
山崎
今は設計者ごとにやり方を変えています。例えば、谷尻誠さんとは現在、山口県柳井市で高校跡地に複合図書館を建設するプロジェクトが進んでいるのですが、僕たちは基本設計の手前まで条件を整理しました。谷尻さんはそれを全面的に踏襲するかたちで設計を具体化してくれています。他方で、設計者自らワークショップに参加することで、僕たちの条件整理よりも先に設計案があがってきた《信毎メディアガーデン》(2018)のようなプロジェクトもあります。この設計を担当した伊東豊雄さんとスタッフの方々は、僕らがワークショップの意見をまとめるのと並行してスタディをはじめてくれていました。早い段階でプランのようなものが先に出てきたので、僕たちはそれにすこし描き加えては戻すといったかたちで一緒に与条件を整理するやり方になりました。設計者によってプロセスはさまざまですね。
浅子
そのノウハウも1、2件のプロジェクトを消化しただけでは得られないものですよね。膨大な蓄積があってこそ、設計者の動きに対応できるのだと思います。ところで、以前は「デザインをしないこと」を掲げるのに抵抗はないかとよく訊かれたそうですが、『コミュニティデザインの源流』(太田出版、2016)のなかで山崎さんは、「退屈でつまらない労働、心身をすり減らすような奴隷労働を終わらせよう」というウィリアム・モリスの言葉を引いています。こうした考え方はハンナ・アーレントが『人間の条件』で論じた「ワーク」と「レイバー」の違いにも通じると思いますが、つくる喜びがあるからこそ僕たちも設計の仕事ができる面があります。それを最もよく知っているはずの山崎さんがつくることから離れる決断したのは、わかるようでわからない部分もあります。ワークショップやコミュニティデザインの仕事のなかにもつくる喜びを感じられる面があるのでしょうか?
山崎
アーレントによれば、建築的な職業は「ワーク」に位置づけられますね。何かをつくり後世に残すことがワークであり、やりがいのあるものだと。モリスもそれに近いことを言っていますが、僕自身の皮膚感覚で言うと、ワークショップはレイバーではなくワークに近いものです。例えば、こんなツールを使うとみんなが盛り上がるだろうと考えて工夫してみる。これはとてもやりがいのあることだし、それこそ後世に残る仕事だと思っています。建築設計と同等、またはそれ以上の価値が僕のなかにあるんです。
そんな具合でstudio-Lを設立して5、6年は、僕たちなりにコミュニティデザインを模索する期間でした。そうするうちに東日本大震災が起こります。コミュニティデザインの仕事をしていたのだから、東北でもずいぶん仕事があったんじゃないと訊かれることも多いのですが、東北の復興にはほとんど声がかからなかったのが実際です。僕たちも何かできることがあるはずだと意気込んでいたのですが、結局どこからも呼ばれなかった。東北の人たちに聞くところでは、震災直後に大手コンサルなどの人たちがボランティアとして集中的に駆けつけていたそうです。彼らが将来の復興計画を役場職員とともに短期間で立案し、ゼネコンがそれを引き継いで具体化するといった連携がほぼすべてのエリアでとられていたと言います。そこにコミュニティデザインや住民参加のまちづくりが入り込む余地はなかったのでしょうね。そのような大人の事情で動く世界がある一方、メディアではコミュニティや人のつながりを重視しようといった話題が取り沙汰されました。僕もさまざまな場所に呼ばれて話をしましたが、仕事にはほとんどつながらなかったですね。
浅子
それは意外というか、僕自身が完全に思い違いをしていました。山崎さんは震災後、東北芸術工科大学にコミュニティデザイン学科を立ち上げ、学科長として自ら教育にも携わっていますよね。メディアでの露出とともにこうした話題も手伝って、てっきり山崎さんは東北の現場でも仕事をしていると思っていましたが、実際には、東北ではほとんど仕事なかったと。では、この間はどのような活動をなさっていたのでしょう。
山崎
震災後、話を聞きたいと僕にアプローチしてくれたのは医療や福祉の分野の人たちでした。いろいろなメディアで話をしたことが功を奏したとしたら、彼ら彼女らに「コミュニティデザイン」という言葉が響いたことです。すこし脱線しますが、どうしてそうなったかをお伝えするためにこの分野の動きもお話ししたいと思います。
医療・福祉の世界へ──地域モデル時代の到来
山崎
じつは医療・福祉の分野で、2000年に潮目が変わる大きな出来事がありました。介護保険法の施行による、介護保険制度の実施です。これによる最も大きな変化のひとつは、介護施設の利用者(被介護者)が自分でサービスの種類や事業者を選べるようになったことでした。それまでの介護は「措置の時代」と呼ばれ、要介護認定を受けた高齢者が特別養護老人ホーム(特養)に入る場合、あらかじめ地域が指定する施設にしか入れない仕組みでした。それが介護保険法の適用によって、利用者と介護施設が契約を結ぶかたちに変わります。そして、介護される側が施設を選べるようになったことで、介護施設側も個々の長所をアピールする必要に迫られました。これにともない、それまで社会的に切り離されていた医療と福祉のサービスを組み合わせることもできるようになりました。すると施設の種類も多様化します。社会福祉法人が認可を受けて開設する特養や有料老人ホーム(有料)に加え、医療法人とセットになることで医療サービスを行える介護老人保健施設(老健)なども登場しました。こうした違いを持ちながら、2000年以降には医療と福祉が連携して地域の介護を本気で考えなくてはならない状況が訪れたのです。「措置の時代」から「契約の時代」に変わり、より正しい経営が求められるようになって、介護施設では長い模索の時期に入ります。どうやって地域の意見を聞くか、自分たちは何をすべきかと考えるなかで、どうやらコミュニティデザインという言葉が医療や福祉の分野の人たちの耳にも届いた。僕のもとに地域の社会福祉法人や社会福祉協議会などから講演の依頼が舞い込むようになったのは2012年ごろですから、みんなずいぶん長い間、困っていたのでしょう。
浅子
たしかに2000年に介護保険法が施行されてから10年以上が経っていますから、ずいぶん長い模索期間だったことになります。2012年ごろというと震災後の比較的早い時期でもありますね。
山崎
反応は早いですよね。メディアの力も大きかったのでしょう。僕たちもその後次第に、福祉関係の人たちと話をする機会が増えていきました。そうこうするうち、厚生労働省が「地域包括ケアシステム」を推進しはじめ、介護の分野では2014年ごろから「地域とのつながり」というテーマが浮上します。被介護者が、住み慣れた地域でその人らしい暮らしを続けることを目的にした包括的な支援・サービスの提供体制として、介護と医療のつながりが求められるようになりました。この「医介連携」には、高齢者や介護者の日常復帰を促すための自立支援の仕組みをつくるねらいがありました。病院での入院期間に上限を設け、長引く場合には介護施設に移り、リハビリテーションを通じて自立を支える。それを推進した結果、日本中の大規模病院に地域連携室が設けられました。しかし、ここで言われる地域とは病院にとって介護施設のことでした。地域連携室にはメディカル・ソーシャルワーカー(MSW)と呼ばれる社会福祉士の人たちが勤務しているのですが、実態としては、退院を早めなくてはならなくなった入院患者を介護施設に移すための手配に終始している部分があったのです。僕がお話を伺った社会福祉士の人たちは、自分たちが連携しているのは本当の地域じゃないんだよと言い、なかにはMSWを自嘲気味に「メディカル・サンドウィッチ」と呼ぶ人もいました。早く退院させたい病院側と多くの入居者を受け入れきれない介護施設との間で、地域連携室は板挟みになっていたのです。
ただ、厚労省の示す地域包括ケアのイメージ図を見ると、この仕組みづくりは医療と介護だけの問題ではないこともわかります。よく知られた植木鉢のモデルがあるのですが、この図では「住まい」も重要な場所に位置づけられています。つまり、「医療・看護」「介護・リハビリ」「保健・福祉」の3本柱の基盤は、あくまで在宅で介護できる住環境であるとしているんです。例えば、家のなかに段差があったり、熱効率が悪いとヒートショックのおそれがあったり、階段に手すりがなかったりすると、高齢者は帰りたくとも帰れません。だから、その環境を整えましょうといった方針も盛り込まれている。これは明確に建築的な課題ですよね。でも医療や福祉の人たちにとってはまったくの異分野なので、まずアプローチの方法がわからない。メディカル・サンドウィッチを続けざるをえない状況で、しきりに「コミュニティデザイン」と言っていた僕がこの人たちの視界に入ったのは、こうした背景もあるのではないかと思います。
もうひとつだけ付け加えるならば、住環境を整え、在宅での介護を推進した結果、家庭の負担が増大することも課題として指摘されています。「地域包括ケアシステム」のもうひとつのポイントは、訪問介護や在宅医療を強化しながら、地域の人たちが総ぐるみで介護に参加できるようにすることです。例えば、認知症の高齢者が徘徊していれば、地域の人たちが家に連絡して送り届ける──、こういうあたたかい地域づくりが実現できれば、誰もが歳をとっても同じ地域に住み続けることができます。「地域包括ケアシステム」にはこうした理想も込められていました。ところが、ここにも医療・福祉の人たちにとってのハードルがあります。彼ら彼女らがこれまで相手にしてきたのは病名がついた人たちだったからです。病気でもない元気な人にどうやってアプローチすればいいのか、それすらもわからないなかで、これは絵に描いた餅だろうとみんな手をこまねいていました。

厚労省が推進する地域包括ケアシステムのイメージ
出典=地域包括ケア研究会研究事業報告書「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」(2016)
浅子
医療や福祉の分野の人たちはただでさえ忙しい実状があるなかで、建築の世界や地域とのつながりというのはブラックボックスだったのですね。そのため、山崎さんが登場するまではほとんど手つかずのままだったと。
ケアするまちの先駆者たち
山崎
他方で、すでに先進的な取組みを行っている施設もありました。そういうところが地域包括ケアシステムのモデルになっています。人手が足りないにもかかわらず、ほとんど熱意だけで地域の課題を克服しているような人たちの動きを厚労省がキャッチし、これを全国的に広めようという動きにつながったのが地域包括ケアシステムの仕組みづくりでした。そのひとつが、新潟県長岡市の「高齢者総合ケアセンターこぶし園」。僕も昨年出版した『ケアするまちのデザイン──対話で探る超長寿時代のまちづくり』(医学書院、2019)で、総合施設長の吉井靖子さんと施設の建築設計を手掛ける高田清太郎さんにくわしく話を聞いています。
「こぶし園」は長岡市の市街地から離れた場所に1983年にオープンした特養です。100床備えた大規模集約型の特養として、開設後は活気のある施設運営が行われていました。しかし、人里離れた立地は利用者やご家族に「遠い場所に置いていく」意識をもたれていた。そこでこぶし園は、施設機能を地域に点在させる運営方式に転換します。2002年に第1号となるサポートセンターを開設したのを皮切りに、その後も数を増やし、現在は旧長岡市内に18カ所を構えるまでになりました。
これを積極的に推し進めたのが前総合施設長の故・小山剛さんです。100床というのは被介護者が「措置」されていた時代に典型的な特養のつくり方でした。小山さんは入居者が家に帰りたいと言っているのを聞き、措置の時代が終わりを迎えているのを感じた。そこで、町全体を特養と見立てることはできないだろうかと考えはじめます。いきなり自宅に帰すのは難しいけれど、町のなかに小規模な特養をつくることができれば自宅のように過ごしてもらえるのではないか、訪問看護ステーションからすぐに医療スタッフが駆けつけられるようにすれば、同等のサービスが提供できるんじゃないかと。そうしてこぶし園は町ぐるみ旅館ならぬ町ぐるみ特養を実現させてしまったんです。
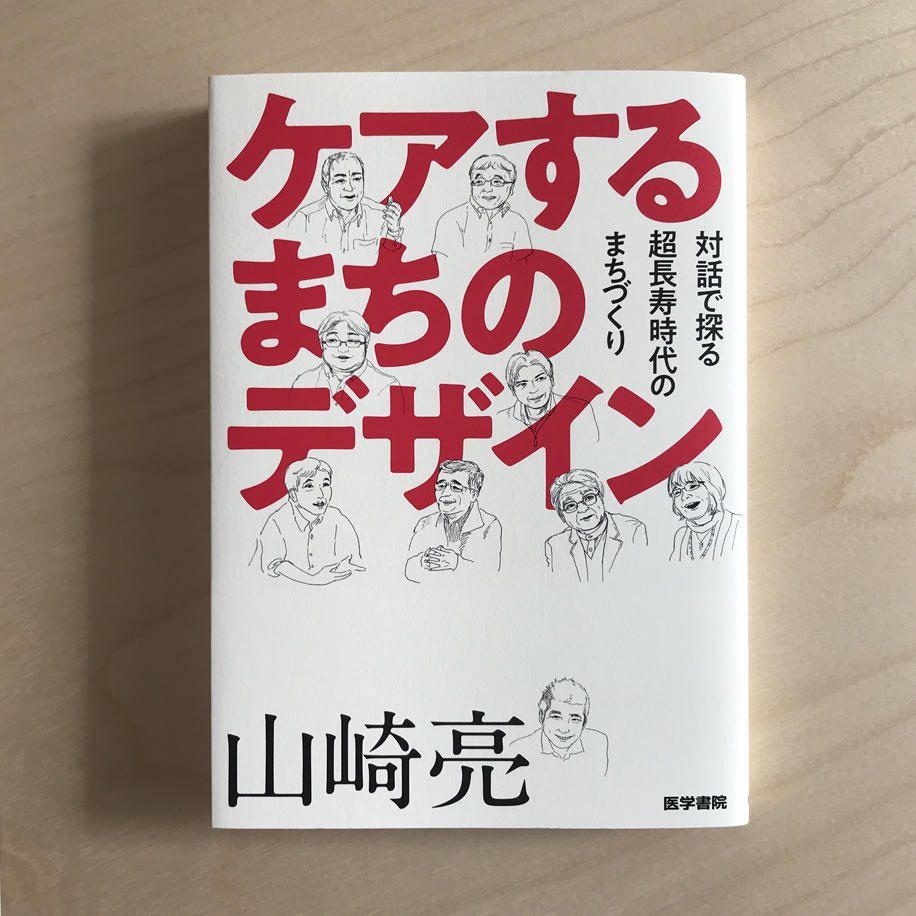
『ケアするまちのデザイン』(医学書院、2019)

こぶし園のサポートセンター
提供=studio-L
浅子
それにしても小山さんの行動力はすごいですね。とても現代的な考え方だと思います。ところで、今のお話でひとつ気になったのは施設を分散させることです。僕も設計事務所にいた時代に特養を担当したことがあるのですが、とにかく許認可を受けるのにたいへん苦労したおぼえがあります。小さい規模でも営業の許可が下りるのでしょうか。
山崎
さすがにくわしい! おっしゃるとおり、特養を開くには一定規模の床面積と床数が求められるので、小規模のものを単独でつくることが難しい。そこで小山さんが思いついたのは、市街地から離れた建物を本部機能として残しつつ、町のなかのほうをサテライトと位置づけることでした。そうすれば、10-15床程度の小規模特養でも認可が受けられます。実際、もともとあった4階建ての建物は今も事務局として、1階部分だけを数名のスタッフが使っている状態なんです。
一見するとズルいやり方のようですが、こうした仕組みが効果を上げているからこそ、厚労省も注目したのでしょう。こぶし園では介護の必要がなくなって自宅に戻った人もいるんです。さらに、こうした高齢者の自宅にはタブレットを備え付け、何かあればそれがナースコールにもなるようになっている。緊急時には訪問介護ステーションから5分以内にスタッフが駆けつけてくれるので問題ありません。小山さんは特養の部屋で行っていたことをまちに展開しただけだと言っていたそうですが、先見の明があるすぐれた運営ですよね。
浅子
かなりアクロバットな方法ですが、地域のなかで高齢者を見守るという昔からのやり方に回帰しつつ、タブレットのような新しい技術と組み合わせて実現しているのはじつに現代的な発想ですね。将来的にそうなってほしいと思えるようなやり方を先取りしていて、こうした事例をモデルにするのはけっして間違っていないと思います。その一方で、床面積や床数の話のように、小規模施設の需要が高まっている実態と現行の法規がずれていることにはおかしな印象も受けます。厚労省もそれを把握しているのだとすれば、本来は運営者側のやり方ではなく法律から先に変えてほしいところですよね。
山崎
はい。厚労省もその後、小多機(小規模多機能型施設)を認可する新しい枠組みをつくりました。地域包括ケアを具体化するならば、こぶし園のような分散型の施設づくりの仕組みも導入できるようにしなくてはいけませんし、それを特養や有料、グループホームなど多様化した介護サービスとも組み合わせられる必要がある。小山さんたちが試行錯誤していた時代に比べると今は実現しやすい状況が整ってきたと言えます。
浅子
なるほど、おもしろいですね。現場で先進的な試みを行っている人たちに厚労省が着目し、それを普及させるビジョンまで示した、とはいえほとんどの施設ではなかなか追従できずにいたというのが2010年代前半までの状況ですね。そこにコミュニティデザインを提唱していた山崎さんに白羽の矢が立った。山崎さん以外にそういうことをやっている人はいなかったのでしょうか。
山崎
建築業界には福祉系の施設を専門に設計する人たちもいますが、地域をつなぐという視点からまちづくりや都市計画、建築設計と医療・福祉の両方に幅広く関わっている人はあまりいなかったように思います。ですが、『ケアするまちのデザイン』を読んでいただければ、介護の分野が建築の専門家に何を期待しているかわかると思います。この本はおもに私と地域包括ケアの現場に携わっている方々との4つの対話から構成されているのですが、みなさんから話を聞くにあたり、医療や福祉の専門家とともに、デザインやまちづくりに携わっている人にも同席してほしいとお願いしました。4篇すべて、私とそれぞれの専門家との鼎談というかたちになっています。こぶし園の取材では、サポートセンターの設計を担当された高田建築事務所の高田清太郎さんにもお話を伺っています。
ほかにもこの本に登場するデザインやまちづくりの専門家はそれぞれの地域でとてもきめ細かく医療・福祉分野からの要望に応えている方ばかりです。そのひとりに、「障害活躍のまち」として政府が推進する日本版CCRCのモデルとなった、「Share金沢」(石川県金沢市)の設計者・西川英治さんがいます。この本では西川さんととともに「Share金沢」をつくった、社会福祉法人佛子園の理事長を務める雄谷良成さんにもお話を伺っています。そのなかで興味深かったのは、雄谷さんが「Share金沢」をつくるときにクリストファー・アレグザンダーの『パタン・ランゲージ』(鹿島出版会、1984)を熟読していたことです。雄谷さんは西川さんとの打ち合わせの前にこれを読み込んで、自分たちがつくろうとしているまちに必要だと思うすべてのパターンに付せんを貼っていたそうなんです。すると、どうなるか。西川さんが出す案にことごとく雄谷さんの反論が入るんです。例えば、「樹齢250年の椎の木を象徴的に……」と言って案を出せば、「神聖な場所というものは突然、ふいに遭遇するものでしょう?」といった具合。クライアントがそんなことを言い出せば、設計者は戸惑いますよね。付せんだらけの『パタン・ランゲージ』の存在を知らぬまま、西川さんは40もの設計案をつくったそうです。くわしくはこの本を読んでいただきたいのですが、このふたりの信頼関係と粘り強さにはとても驚かされました。

パタン・ランゲージの手法でつくられた「Share金沢」の家並み
提供=studio-L
このコラムの関連キーワード
公開日:2020年05月29日

